みなで、同じことを同じ方法で同じスピードでやることを求める学校
小学校って、なぜあんなにみんなで同じことを、同じスピードで同じ方法でやることを求めるのでしょう?人間さまざまで、得意不得意が違うんだから、それぞれができる分野をがんばり、苦手な分野はまあまあできたくらいで勘弁してくれないんでしょうか?
息子は処理速度指標が非常に低く、言語能力が高く差が40以上あるのです。目と手の協調性が悪いので、板書や漢字の書き取り、リコーダーなどが壊滅的といったらかわいそうですが、まあ苦手なのです。
担任に事情を話し、漢字はやや時間を多めにもらうなどの対応をし、板書は間に合わなければ仕方ないという感じでやっています。
字を小さく書くのが苦手なので、息子のノートは字がとんでもなくでかい。だから、あっという間にノートがなくなります。すごい勢い。。。たまに娘のノートを見ると、差にびっくりします。
進級により、新たなる心配が。。。
学年が上がるに当たって心配なのが、音楽。息子の学校は、音楽会や運動会での楽器演奏やマーチングなどに力を入れているのです。高学年になると練習が始まるのです。できない子は、居残りや休み時間も練習に充てられるようです。
はあー、すごく心配。音楽会も毎年とてもレベルが高いように私は感じます。楽器のクラブや合唱クラブもあり、その部員はさらにうまいので全体のレベルも高い。これは、できない子にとってはかなりきつい。
夏休みなどに、毎年課題曲が出て家で練習し動画で先生に提出するテストもあります。毎年夏休みは私とリコーダーやピアニカの特訓もしています。もう大変ですよそりゃ。
「タンタンタタンでしょ?タンタンタじゃないよ。もう(怒)」と二人とも毎回必死。これが高学年になるにつれレベルが上がるので本当に困る。
去年は、やっとできたと動画提出後ほっとしたのもつかの間、先生からのコメントが。
「がんばりました、合格です。でもタンギングの仕方をもう一度教えるのでもう少し頑張りましょう」とのこと。
苦手な子に、「タ、タ、タンギングですか?」もう許してください先生。。。」とすがる母。。
柔軟な対応求む
先生方も少ない職員数の中必死に指導してくれているのもわかります。でも、できない子もいるのをわかってほしい。
WISCを受けた際の心理士の方からは、できないことはいくらがんばってもできません。苦手が前より少し苦手になるだけですと言われました。もちろん、できないことにも挑戦することも大事だけど、苦手なことに多くの労力を費やすなら、得意なことに費やした方がよっぽど伸びると思うんですよね。
苦手なことは、得意なことでどうにかできる程度にしておいて、後は、得意なことに力をそそいでも非難されないような環境がいいな。
大人にも当てはまりますよね。でも昭和の教育を受けてきた母にとっては、「苦手をいくらやっても少し苦手になるだけ」という言葉におののきました。もっと早く教えてほしかったよ。
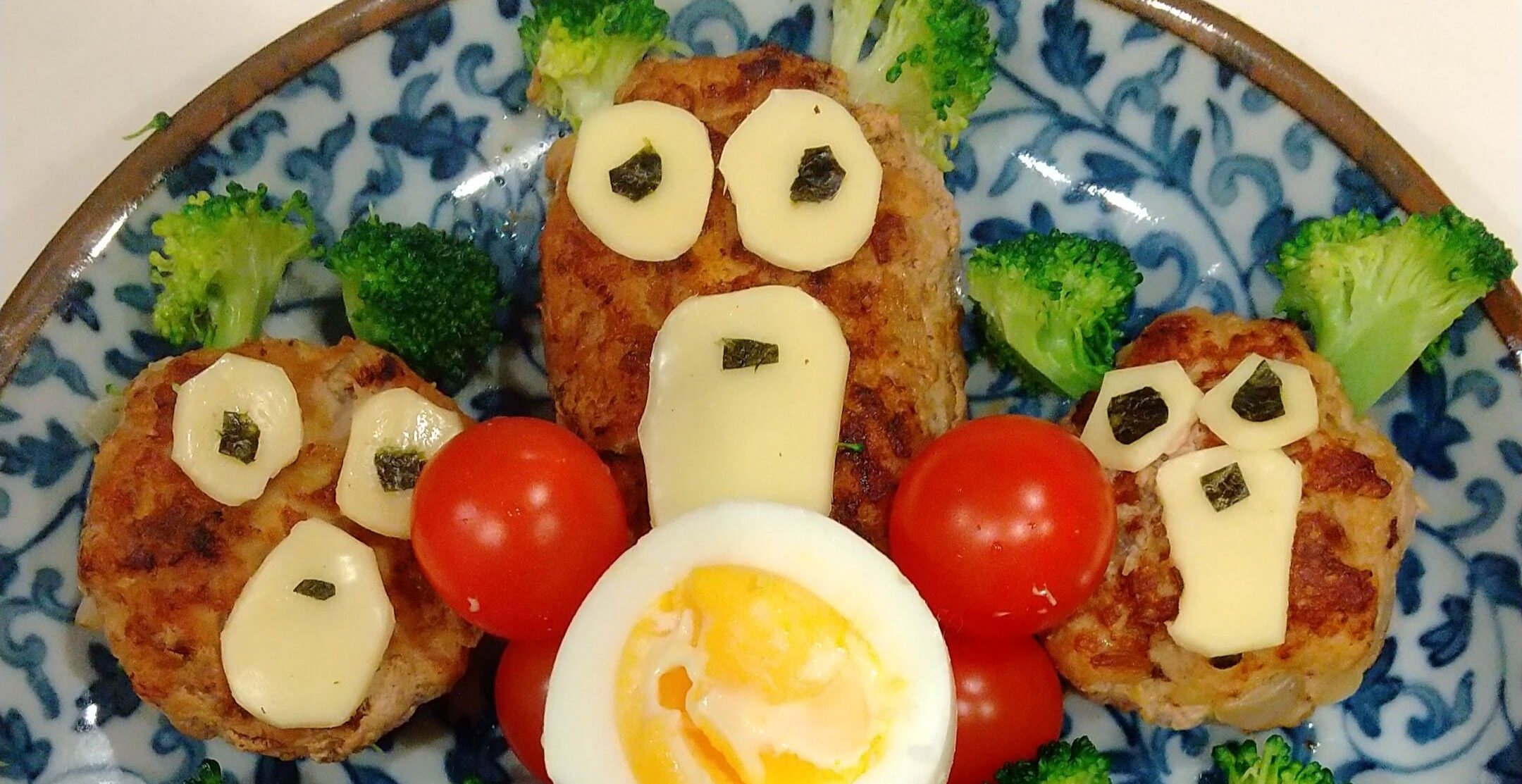


コメント