なぜか習い事が続かない
息子は習い事がなかなか続きませんでした。スイミング、体操教室、サッカーなど。姉と一緒に初めても、姉は順調に進級していくのになぜか息子は怒られてばかりで進級せず。特に運動神経が悪いわけでもないのになぜ?と思うことが多くありました。
本人が場面の切り替えについていけなかったのと、コーチに本人の特性を理解してもらえなかったことが原因だったと、後からわかりました。これについても、通級の先生と話していて気づかされたことです。
習い事は、当たり前ですがコーチの話を聞いてその練習をしていきます。個別の練習をしたり、グループで練習したり、最後に試合をしたりなどなど。1時間の間に場面の展開が多くあります。息子は、聴覚より視覚優位なので、全体に口頭での指示だけではついていけないのです。なので、次に何をやるのか理解しないまま自分の番が来て怒られるということが続き、いやになりやめるということが起きていたのだと思います。
発達特性のある子が習い事を探すときに気を付けることは?
小学3年夏に頭を叩いたりチック症状が出たときに、一度すべての習い事を辞めました。その後何か本人に自信を持ってもらいたくて、いろいろ探しました。何個か体験に行き、卓球を始めました。今も通えているのですが、その理由は、コーチがいいです。本人との相性もよかったのと、こちらから特に特性については話していませんが、一斉指示のあとに、個別に声をかけてくれたり、本人への注意をするときには、必ず名前を読んで目が合ってから、助言や注意をしてくれています。うまくいった時もうまくいかなかった時も、理由も含めてこまかくフィードバックしてくれるのです。本当にあのコーチはすごい。
習い事は、大変ですが初めは毎回付き添っていました。なので、親は終了後必ず挨拶してコーチともコミュニケーションを積極的にとるようにしました。すると、親にもよくなってきているところなどを教えてくれますし、本人も安心するんじゃないのか?と思っていました。今では、「もう僕一人で行けるから大丈夫」とのことで、帰りの迎えだけ行っています。
通級の先生からも、本人の特性を理解してくれるコーチを探すことが一番重要と言われました。やはりスポーツ業界では、発達特性の理解はまだ進んでいないし、昔からの厳しい指導をするコーチも非常に多いと言われました。本人にできないことをやらせるのは無理。本人にあった環境を探すことが重要なので、親がよく確認しなければいけないんだなと思います。以前サッカーの体験で、体験では少人数だったので細かい指導で大丈夫そうと入ったら、実際の練習は大人数だしコーチが細かく指導できる体制ではなく結局やめたということもありました。なので、結局は実際に始めないとわからないこともたくさんあります。お金も手間もかかるので大変ですが、ひとつひとつやっていくしかないんだなと実感しました。
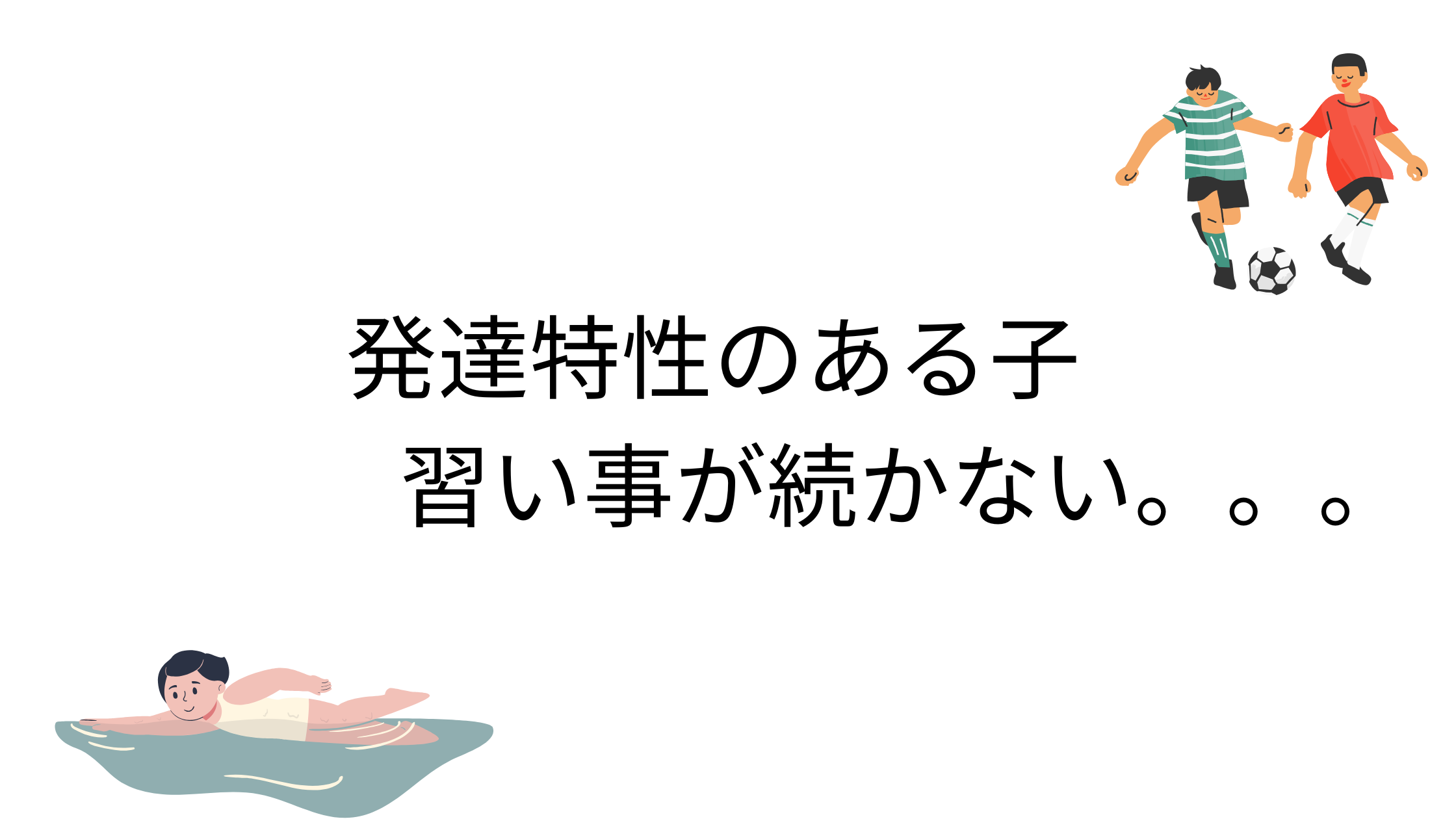


コメント